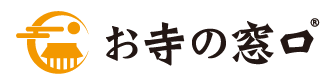包括遺贈と特定遺贈
「包括遺贈」とは相続財産の全財産を割合指定することで渡す方法です。例えば「Aに全財産の三分の一を渡す。」や「Bに全ての財産を渡す。」といったようにすることができます。「包括遺贈」はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぎます。包括受遺者は、遺贈を放棄することもできますが、遺贈を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所において放棄の手続きを行う必要があります。また財産を割合で指定されている場合は、具体的に配分をしようとすれば、どの財産を取得するかが決まってないので、他の相続人と相談する必要があります。他の相続人と一緒に遺産分割協議を行うこととなります。
次に「特定遺贈」とは財産を特定して渡す方法のことを言います。例えば「自分の財産から、土地1をAに、土地2をBに渡す。」ということができます。
特定遺贈は指定されているため財産内容の変更ができません。先ほどの例題で説明すると、遺言書を書いた時点では土地A(2000万円)をAに、土地B(2000万円)をBにというように、公平に財産を分けるつもりであっても、いざ相続が発生したときは、土地Aが値上がりしていて3000万円に、土地Bが値下がりしていて1500万円になっていたという事態が起こったとしても変更することはできません。
また、特定遺贈の受遺者も、遺贈を放棄することができますが、包括遺贈と違い放棄するのに期限はありません。しかし、特定遺贈の受遺者が、遺贈を受けるのか放棄するのかがわからない場合は、遺贈義務者は相当の期間を定めて、その期間内に遺贈するかを決めるよう催告することができます。受遺者がその期間内に意思を表示しなければ、遺贈を承認したとみなされます。
◾️相続に関する相談はこちらまで