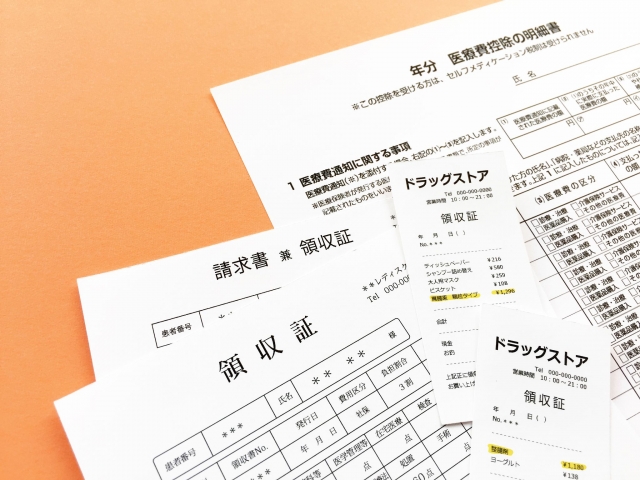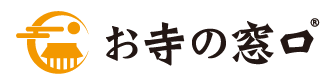「専門家の窓口」では現代社会において寺院が直面する様々な問題に焦点を当てます。
住職様へのインタビューを通じて、お寺が抱える具体的な課題を深く掘り下げ、その本質に迫ります。
さらに、各分野の専門家から得られた貴重なアドバイスと深い知見をご紹介します。
寺院運営の新たな可能性を探り、より良い未来を築くためのヒントを提供します。
はじめに:お寺の現場で起きる未払い問題の現実
お寺の運営に携わる人々にとって、檀家(だんか)さんとの関係は大切な基盤です。
しかし、近年、未払いのトラブルが増えているという声を耳にします。これは単なる金銭的な問題ではなく、信頼関係の崩壊や社会的な変化が背景にあります。
今回、インタビューしたお寺の関係者の方々の体験談を基に、未払いの実態を掘り下げてみましょう。
これらの話は、葬儀や法要、骨預かりにかかる費用が未払いになるケースが主です。未払いはお寺の運営を圧迫するだけでなく、精神的な負担も大きいものです。
未払いの典型的なパターン:骨預かり管理費のケース
詳細に語られた未払いの事例は、骨預かりに関するものです。
あるお寺では、父親の葬儀を執り行った檀家さんが、事情により骨を預かってほしいと依頼しました。
49日法要もお寺で実施し、お布施として1万円、骨壇の管理費として年間2万円を約束しました。
しかし、息子さんが法要に参加したものの、費用をその場で支払わず、後日払うと言い残して去ってしまいました。
以降、電話で催促しても「お盆に行くのでその時払います」「来月払います」と繰り返すばかりで、実際には支払いがなく、2年間にわたって引き伸ばされました。
このケースでは、骨預かりの管理費が積み重なり、総額で8万円近くに膨れ上がりました。
お寺側は内容証明郵便を送付し、簡易裁判所での少額訴訟を検討しましたが、相手の住所が変わったため、訴訟提起できる裁判所の管轄がお寺と離れた遠方の裁判所となってしまったため実行しませんでした。
最終的に、着払いで骨を送り返す形で決着しましたが、お寺側は「お金はいらないから関わりたくない」と諦めざるを得ませんでした。
このような未払いは、単に経済的な損失ではなく、相手の言い訳の多さが精神的なストレスを生みます。
未払いが起きる背景:社会変化と倫理観の低下
なぜ未払いが頻発するのでしょうか?との問いでは、他のケースと同様に5〜6年前から急増したと指摘されています。
昔は地域コミュニティのつながりが強く、未払いは評判を落とすため稀でした。
しかし、檀家さんとの関係性の希薄化に加え、ネットの普及や便利になったソリューションが増え、倫理観が希薄化した結果、急増しています。
例えば、送り人(葬儀社)経由の檀家さんは、住所すら明かさないケースがあり、追跡が困難です。また、経済的な事情だけでなく、「払うと言っているのに」と逆ギレする態度が問題を複雑化します。
インタビューでは、未払いの被害額が小さいため、法律相談の費用の方が高くつく点も挙げられました。
少額訴訟は通常訴訟と比べて負担が軽く利用しやすいですが原則として相手住所地の裁判所に出向く必要があり、遠方だと交通費がかさみます。
実際、内容証明を送ったところ半額だけ振り込まれたケースもありましたが、残額は未払いのまま。こうしたトラブルは、お寺の運営を圧迫し、ボランティア的な側面を強いています。
未払い対策:予防と対応のポイント
未払いを防ぐためには、事前の契約書作成が有効です。
加えて前払いの導入を検討すべきです。また、葬儀社との連携を強化し、信頼できる紹介元を選ぶことも重要。
対応策として、弁護士相談のハードルを下げるホットラインの必要性が議論されました。
お寺同士のネットワークで共有したり、無料相談窓口を設けたりする取り組みが有効です。
結論:未払いは信頼の崩壊を招く
未払いのトラブルは、お寺の存続を脅かします。檀家さんにとっては一時的な出費ですが、お寺側は管理や精神的な負担を強いられます。
未払いは「払う払う詐欺」のような形態が多く、骨預かりが絡むと深刻化します。
社会全体で倫理観を高め、お寺と檀家の関係を再構築する必要があります。
「専門家の窓口」の支援
「専門家の窓口」は、未払い問題の解決を総合的に支援します。
オンライン相談で専門家にアクセスし、オンラインチャット形式で気軽に相談ができるシステムを近日公開予定です。
事例共有の掲示板で他寺のノウハウを学び、月500円程度のサブスクリプションで費用を賄うモデルを提供予定。
未払い問題は、お寺の財政と土地管理に深刻な影響を及ぼしますが、専門家のサポートとデジタルプラットフォームの活用で解決可能です。「専門家の窓口」を通じて、効率的な手続きと予防策を導入し、あなたのお寺の未来を守りましょう。
詳細は「専門家の窓口」にお問い合わせくださいませ。
https://senmonkanavi.com/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/